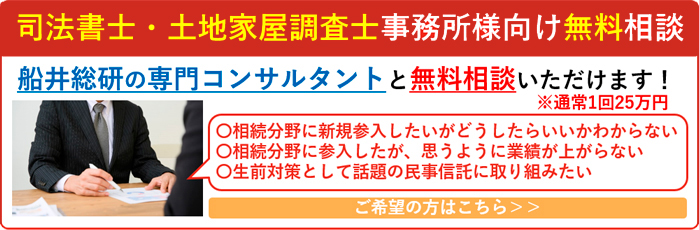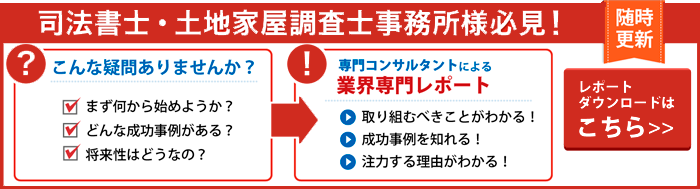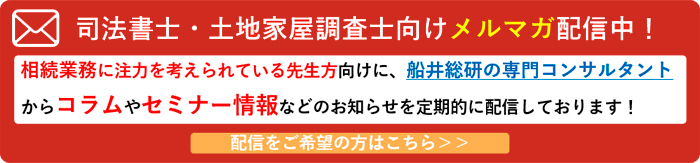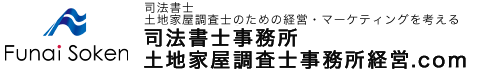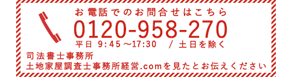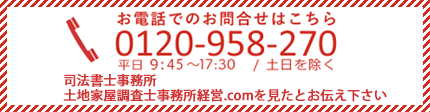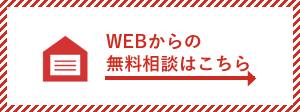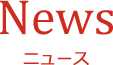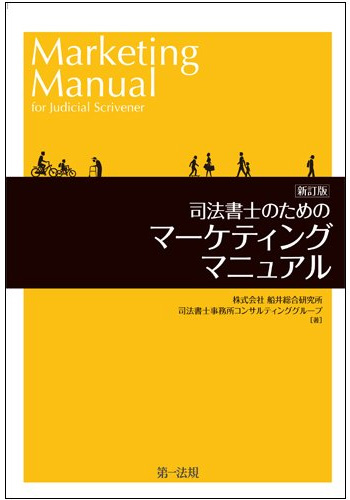士業事務所は生成AIをどう生かしていくべきか

皆様、こんにちは。
株式会社船井総合研究所の清水です。
今回のコラムでは、「士業事務所が生成AIをどう生かしていくべきか」についてお伝えいたします。
① 生成AIによって変化する士業
② 生成AI時代を生き抜く士業事務所とは
③ 士業事務所の生成AI活用事例
生成AIによって変化する士業
AIによって消滅する職業””として挙げられることも少なくない士業。以前は「専門的領域のためコンピュータには困難」や「まだ実用的ではない」などの楽観的な声も多くありましたが、技術の進歩により、生成AIによる業務の代替が現実的になってきています。
実際、契約書のレビューや申請書類の作成など、すでに生成AIにより大きく効率化に成功したような事例も出てきており、士業者の業務内容や、必要なスキルセットは変化しつつあります。
それでは、実際に生成AIによる置き換えが進む中、士業事務所が生き抜いていくためには何が必要なのでしょうか?
生成AI時代を生き抜く士業事務所とは
生成AIの時代において、士業事務所がさらに成長していくためのポイントを3つご紹介します。
①戦略的な生成AI導入
業務における生成AI活用は今後必須となっていきますが、””どこで活用するか””が重要です。
まずは業務を棚卸したうえで、人間とAIの担当業務を戦略的に判断することが不可欠です。
②AI活用スキルの向上
生成AIを業務に導入しただけでは、必ずしも業務効率化ができるとは限りません。うまく扱えるかどうかは担当者のAIへの理解度に依存します。
生成AIの仕組みや活用方法、リスクについて正しく理解する必要があります。
③受任スキルの向上
AIによる業務処理の効率化により、同じ時間でより多くの案件を処理できるようになるため、合わせてより多くの案件を受任していくことが可能になります。
事務所がさらに成長していくためには、案件数向上のためスタッフの受任力も高めていくべきでしょう。
それでは、士業事務所はどのように生成AIを活用しているのでしょうか?
士業事務所の生成AI活用事例
本章では、士業事務所における生成AIの活用事例を4つご紹介します。
①遺言書の文案作成
遺言書の作成にあたり依頼者の状況を入力することで、生成AIがその状況に最適と判断した遺言書の文案を作成します。
文案は事前に型を学習させておくことで、作成したい形式に合わせての出力が可能です。
②申請書のチェック
業務上の負担が大きいチェック業務も、生成AIで効率化が可能です。
作成した申請書と元となる書類を照らし合わせ、記載内容に間違いがないかをAIが判断します。
③業務マニュアルQ&A
業務マニュアルと生成AIを組み合わせることで、業務で分からないことがあった時に生成AIに質問することができます。
普段の業務での活用はもちろん、新しくスタッフが入った際の新人教育にも最適です。
④面談内容のフィードバック
受任力向上に不可欠な面談のフィードバックにも生成AIを活用できます。
面談の録音や文字起こしをアップロードするだけで、評価軸に合わせて生成AIが適切なフィードバックを行います。
今回のコラムでは、「士業事務所は生成AIをどう生かしていくべきか」についてお伝えしました。
改めてにはなりますが、生成AI時代に成長する事務所になるためには以下の3点を抑えるべきです。
①戦略的な生成AI導入
②AI活用スキルの向上
③受任スキルの向上
まだ生成AIを導入していない事務所は、本コラムでお伝えしたように、今すぐに業務の棚卸から始めることをおすすめします。
“何から始めればいいかわからない”、”事例について詳しく知りたい”などあれば、お気軽にご相談ください!